「休職中の給料はどうなるのか」「生活費は本当に大丈夫なのか」と不安を抱えていませんか?実際、会社員の約7割が休職制度の利用経験や知識がなく、給与が減額・停止されるケースも少なくありません。例えば、私傷病による休職では、健康保険の傷病手当金を利用して【標準報酬日額の約3分の2】が最長1年6か月支給される一方、会社規定によっては無給となる場合もあるため、制度の違いを知ることが重要です。
また、労働基準法や就業規則、雇用形態別の対応によって、受け取れる給与・手当の内容や申請方法は大きく異なります。さらに、休職理由がうつ病や妊娠・介護の場合には、それぞれ適用される手続きや支給条件も異なるため、「自分の状況に合った正しい情報」を知る必要があります。
知らないまま放置すると、「数十万円単位の損失」や生活設計の崩れにつながることも。この記事では、休職給料の仕組みから具体的な計算例、公的給付の全容、生活費の見直し方法まで徹底解説します。
今の不安を確実に解消し、安心して休職期間を乗り切るための知識を、最初から最後までぜひご覧ください。
休職とは何か?基本定義と休職・欠勤・休業の違い
休職とは、従業員が一定期間業務から離れることを会社が認める制度で、主に私傷病やメンタル不調、自己都合、公職就任などさまざまな理由で適用されます。休職は一般的に就業規則に基づき、会社の承認が必要です。欠勤や休業と混同されやすいですが、それぞれ法的・制度的な位置付けや給与への影響が異なります。
休職の種類と特徴 – 私傷病休職、自己都合休職、公職就任休職など主要な休職形態を説明
主な休職の種類と特徴は次の通りです。
- 私傷病休職:うつ病や適応障害などメンタル不調、病気やケガが理由で働けない場合に認められるものです。診断書の提出が必要で、期間や条件は会社によって異なります。
- 自己都合休職:家族の介護や留学など、従業員自身の希望に基づく休職です。会社が認める場合に限り、適用されます。
- 公職就任休職:選挙で公職に選ばれた場合や、一定の公的な業務に従事する際に取得できる休職です。
休職理由によって支給される給料や手当に違いが生じるため、事前に会社の就業規則をよく確認することが重要です。
休職と欠勤・休業の法的・制度的違い – 労働基準法や就業規則に基づく違いと給与への影響を整理
休職・欠勤・休業には明確な違いがあります。
| 区分 | 定義 | 給与 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 休職 | 会社の承認で一定期間職務を離れる | 原則無給(手当支給の場合あり) | 就業規則 |
| 欠勤 | 無断または正当な理由なく仕事を休む | 無給 | 労働契約 |
| 休業 | 労働者の責によらず業務できないとき | 休業手当(平均賃金の6割) | 労働基準法26条 |
休職は多くの場合給与が支給されませんが、傷病手当金など社会保険からの給付を受けられるケースがあります。休業手当は会社都合で働けない場合に限り、平均賃金の6割が支払われます。欠勤は無給となることが一般的です。
アルバイト・パート・契約社員の休職制度 – 雇用形態別の休職可否や給与の扱いについて解説
正社員以外の雇用形態では、休職制度の適用や給与の扱いが異なります。
- アルバイト・パート:多くの企業で休職制度が適用されないことが一般的です。病気やケガで長期に働けない場合、シフト調整や契約終了となる場合が多く、給与の支給はありません。
- 契約社員:契約内容や勤務先の就業規則によっては休職制度が設けられていることもありますが、正社員と比べて条件が厳しい場合があります。給与は休職中無給となることが多いです。
- 社会保険加入者:雇用形態にかかわらず、所定の条件を満たせば傷病手当金が支給される可能性があります。
休職中の給与や手当の有無は、雇用契約や会社の規則、社会保険の加入状況によって大きく異なるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
休職中の給料支給の仕組みと会社規定による違い
休職中の給料支給ルールの法的枠組み
休職中の給料に関する基本的なルールは、労働基準法に基づいています。法律上、労働者が病気やケガなどで働けない場合、会社は原則として休職期間中の給与支払い義務を負いません。ただし、会社都合で休業となる場合には、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です。
一方、病気やメンタル不調による休職では、就業規則や労使協定に従い、給与が支給されるかどうかが決まります。公的制度としては健康保険の傷病手当金があり、支給条件を満たせば給与の約3分の2相当が最長1年6か月間支給されます。
以下の表で法的枠組みを整理します。
| ケース | 給料支給義務 | 支給水準 |
|---|---|---|
| 会社都合の休業 | あり | 平均賃金の60%以上 |
| 病気・私傷病による休職 | 原則なし | 就業規則次第 |
| 傷病手当金 | 社会保険制度 | 標準報酬日額の2/3 |
会社規定・就業規則による支給差異
企業ごとに休職中の給料支給条件は異なります。多くの企業では、休職開始から一定期間は有給扱いとし、その後無給に切り替える例が見られます。
例えば、大手企業の場合は「休職開始から1か月間は給与満額支給、その後は無給」といった規定が一般的です。中小企業では「休職期間中は全額無給」とするところもあります。メンタルヘルス不調(うつ病や適応障害など)が理由の場合でも、支給条件に違いはありませんが、申請に医師の診断書が必要になるケースがほとんどです。
- 休職開始から一定期間は有給
- 以降は無給、もしくは傷病手当金への切り替え
- 診断書や手続き書類の提出が必須
このように、会社ごとの規則を必ず確認し、手続きを漏れなく行うことが大切です。
公務員・教員など特定職種の休職給料事情
公務員や教員の場合、民間企業とは異なる休職制度が適用されます。国家・地方公務員は「病気休暇」と「病気休職」があり、病気休暇期間中は給与の全額または8割程度が支給されることが一般的です。その後の病気休職では給与が支給されない場合が多いですが、職種や自治体によって異なります。
| 職種 | 休暇中の給与支給 | 休職中の給与支給 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公務員 | 全額~8割支給 | 原則無給 | 傷病手当金対象 |
| 教員 | 全額支給 | 原則無給 | 条件により異なる |
| 民間企業 | 会社規定による | 原則無給 | 多様な規則 |
公務員・教員は人事院規則や給与条例に従うため、詳細は所属機関の規定を確認しましょう。
休職中の賞与・昇給・各種手当の扱い
休職中は給与以外の手当や賞与、昇給にどのような影響があるかも気になるポイントです。多くの企業では、休職中は賞与(ボーナス)の算定期間から除外されることが一般的です。そのため、賞与は減額または支給対象外となるケースが多くなります。住居手当や通勤手当、各種福利厚生も休職期間中は支給停止となることが一般的です。
- 賞与:休職期間は算定対象外となり減額または不支給
- 昇給:休職期間中は昇給対象外、復職後に再評価されることが多い
- 各種手当:原則として支給停止
会社の制度や業界慣行によって差異があるため、詳細は就業規則や人事担当者に確認することが重要です。
休職理由別の給料と手当の違い(うつ病・適応障害・身体疾患・介護・妊娠など)
うつ病・メンタル不調による休職と給料の実態 – 傷病手当金の受給条件や給料の扱い、復職時のポイントを解説
うつ病やメンタル不調で休職する場合、多くの企業では給料は全額支給されず、無給や一部減額となるケースが一般的です。会社の就業規則によっては、一定期間のみ給与の一部を支給する場合もありますが、長期化した場合は「傷病手当金」が生活を支える重要な制度となります。傷病手当金は健康保険加入者が対象で、連続3日以上仕事を休み、4日目以降に賃金が支払われないときなどに申請が可能です。支給額は標準報酬日額の約2/3で、最長1年6カ月受給できます。復職時は主治医の意見や職場と連携し、無理のない復帰プランを立てることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給の有無 | 就業規則や会社独自の制度で異なる |
| 傷病手当金 | 標準報酬日額の2/3が最長1年6カ月支給 |
| 復職ポイント | 医師の意見書・職場との調整が必要 |
適応障害・精神疾患での休職給料 – 支給対象や申請手続き、制度の特徴を専門的に説明
適応障害やその他の精神疾患による休職も、一般的に給与全額支給は難しく、無給または減額となる場合が多いです。この際も傷病手当金の活用が基本となります。申請には医師の診断書や会社による休職証明が必要です。精神疾患の場合、休職期間が長引く傾向があるため、会社規則と健康保険制度双方の確認が不可欠です。加えて、会社独自の福利厚生や団体保険で補償されるケースもあるため、自身の加入状況も確認しましょう。
- 傷病手当金申請に必要なもの
- 医師の診断書
- 会社の証明書
-
健康保険証の写し
-
注意点
- 精神疾患の場合、再発防止や職場復帰支援プログラムの利用も推奨されています
身体疾患・介護・妊娠休職時の給料と手当 – 産前産後休業や介護休職の給料支給・公的給付の違いを具体的に示す
身体疾患による休職も、基本的には傷病手当金が中心となります。介護や妊娠・出産に伴う休職の場合は、他の公的給付が利用できます。産前産後休業では「出産手当金」、介護休職では「介護休業給付金」が支給されます。これらの制度は健康保険や雇用保険から給付され、要件や支給額、申請窓口が異なります。
| 休職理由 | 主な手当・給付 | 支給条件・内容 |
|---|---|---|
| 身体疾患 | 傷病手当金 | 標準報酬日額の2/3(最長1年6カ月) |
| 介護 | 介護休業給付金 | 賃金の67%(最長93日) |
| 妊娠・出産 | 出産手当金 | 標準報酬日額の2/3(産前42日・産後56日) |
- 会社独自の支給規定がある場合もあるため、就業規則の確認が必要です
休職に必要な診断書と書類のポイント – 書類取得から会社提出までの流れと注意点
休職を申請する際は、必ず医師による診断書が必要となります。診断書には休職を要する理由や期間が明記されていることが重要です。取得した診断書は人事担当者に提出し、会社所定の休職申請書類も併せて提出する流れです。傷病手当金などの手当申請には、会社や健康保険組合の証明書類も必要となる場合があります。
-
診断書取得の流れ
1. 医療機関で診断を受ける
2. 医師に診断書を作成してもらう
3. 会社の人事担当に提出
4. 必要に応じて追加書類も用意 -
注意点
- 診断書は最新の日付で作成してもらう
- 提出前に内容を確認し、会社規定の書式があれば合わせて用意する
このように、休職の理由や状況によって給料や手当の支給内容は異なり、医師の診断書や各種申請書類の準備が求められます。就業規則や公的制度をしっかり確認し、自身の状況に最適な手続きを進めることが大切です。
休職中に受け取れる手当・公的給付制度の全容
傷病手当金の支給条件と計算方法 – 標準報酬月額を用いた具体的計算例を交え支給期間まで詳細に説明
傷病手当金は、会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった際に健康保険から受け取れる給付です。主な支給条件は、業務外の傷病で労務不能になり、連続3日以上仕事を休み、会社から給与が支払われていない場合です。うつ病や適応障害などメンタル不調による休職でも対象になります。
支給額は「標準報酬月額」の3分の2相当。計算は下記の通りです。
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額(日額) | 標準報酬月額÷30×2/3 |
| 支給期間 | 最長1年6カ月 |
| 必要書類 | 診断書、申請書など |
例えば標準報酬月額が30万円の場合、1日あたり約6600円(30万円÷30×2/3)が支給されます。給与が一部支給されている場合は差額が支給されるため、会社の就業規則や人事担当に確認しておきましょう。
労災保険・雇用保険の休職給付 – それぞれの給付内容と受給手続きの違いを整理
休職理由が業務上の事故や通勤災害の場合は労災保険が適用されます。労災保険の「休業補償給付」は、休業4日目以降から給料の約8割が支給される仕組みです。一方で、自己都合や私傷病による休職は労災対象外となり、雇用保険の給付は原則ありません。
| 給付名 | 対象 | 支給金額 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 休業補償給付 | 業務上・通勤災害 | 給与の約8割 | 会社経由→労基署 |
| 雇用保険 失業給付 | 退職後・求職活動中 | 雇用保険規定額 | ハローワーク |
労災の場合は会社を通じて所定の書類を提出し、雇用保険は退職後にハローワークで手続きを行います。適用条件や手続きには違いがあるため、休職理由や就業形態に応じて確認が必要です。
私傷病休職時の手続き・注意点 – 診断書提出や申請時のよくあるトラブルと対処法
私傷病による休職では、必ず医療機関の診断書を会社に提出する必要があります。診断書には休職期間や病名(うつ病や適応障害など)が明記されていることが求められます。申請の際に多いトラブルは、診断書の日付の不備や、会社への提出遅延、必要書類の記載ミスです。
手続きの基本流れ
1. 医師から診断書をもらう
2. 会社の人事部門へ提出
3. 会社から休職規定や必要な申請書を受け取り記入
4. 健康保険組合や保険会社へ申請
よくあるトラブルと対策
– 診断書の内容不足→医師に記載内容を確認する
– 書類の紛失→コピーを取っておく
– 給付金支給の遅れ→会社と担当部署に早めに確認
適切な手続きを踏むことで、休職中の金銭的不安を軽減できます。休職給料や手当の受給条件は就業規則や契約内容で異なるため、事前に確認し正確に対応しましょう。
休職給料の具体的な計算方法とシミュレーション
休職給料計算の基本式と実践例 – 代表的な計算式と金額例を複数パターン紹介
休職中の給料は、会社の就業規則や休職理由によって大きく異なります。民間企業の場合、休職期間中の給与支給義務はなく、会社独自の規定が支給の有無や金額を決めます。病気やメンタル不調(うつ・適応障害など)で休職した場合は、健康保険の「傷病手当金」が主な収入源となるケースが多いです。
傷病手当金の基本的な計算式は下記の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病手当金の金額 | 直近12か月の標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 |
| 支給期間 | 最長1年6か月 |
| 給与支給がある場合 | 支給額が減額または支給なし |
例えば標準報酬月額30万円の場合、1日あたりの傷病手当金は約6,667円、1か月では約20万円支給されます。会社から給料が一部支給される場合、その差額分だけ傷病手当金が支給される仕組みです。
休職期間別の給料シミュレーション – 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年のケースごとの計算例
休職期間ごとに実際どの程度の金額が受け取れるか、代表的なケースでシミュレーションを行います。ここでは標準報酬月額30万円の場合を例にしています。
| 休職期間 | 支給額(月) | 支給合計 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 約200,000円 | 約200,000円 |
| 3ヶ月 | 約200,000円 | 約600,000円 |
| 6ヶ月 | 約200,000円 | 約1,200,000円 |
| 1年 | 約200,000円 | 約2,400,000円 |
民間企業の場合、休職中は「給料満額」が支給されることはほとんどありません。支給額は「給料の6割程度」となることが多く、うつ病や適応障害での休職でも同様です。公務員や教員の場合は、勤務先の規定により8割支給や一定期間満額保証など独自の制度もあるため、必ず人事部へ確認が必要です。
給料支給が減額・停止されるケース – 給料が出ない、減額される具体的な条件や注意点
休職中に給料が減額または支給停止される主なケースは以下の通りです。
- 就業規則で「休職期間中は無給」と定められている場合
- 病気休職やメンタル不調(うつ・適応障害など)で長期離脱し、会社が給与支給の義務を負わない場合
- 公務員や教員でも、一定期間を超えると支給割合が減る・停止することがある
- 傷病手当金の支給条件を満たさない、または申請を忘れると無収入となるリスク
特に注意したいのは、休職給料が満額支給されるケースはきわめて稀であることです。会社の規定や社会保険の内容を事前に把握し、万が一に備えた資金管理が重要です。また、診断書や申請書類の不備による手当金不支給、休職期間中の副業や転職活動による支給停止などもあるため、細かな規則や手続きについては必ず確認しましょう。
- 休職給料の支払い有無や割合は「会社の就業規則」および「社会保険制度」で異なります
- うつ病や適応障害などメンタル不調での休職も、傷病手当金の対象となる場合があります
- 公務員や教員は民間企業と制度が違うため、必ず職場の人事担当に確認しましょう
このように、休職給料の計算や支給条件には多くのパターンや注意点があります。事前に自分の勤務先の規則や社会保険制度を確認し、安心して休職期間を過ごすための準備を進めてください。
休職中の生活費・収入管理と家計対策
固定費・変動費の見直し方法 – 生活防衛資金の確保や無駄な支出削減の具体策
休職中は収入が減少しやすいため、支出の見直しと生活防衛資金の確保が重要です。まず見直すべきは家賃や保険料、通信費などの固定費です。契約内容の再確認やプラン変更、不要なサービスの解約を検討しましょう。次に、食費や日用品などの変動費についても日々の買い物で節約を意識し、まとめ買いや特売日の活用が効果的です。
支出管理のポイントは下記の通りです。
- 固定費は毎月の支払い額をリスト化し、優先順位をつけて削減を検討する
- 変動費は家計簿アプリやノートで記録し、無駄遣いを見直す
- 生活防衛資金として、手元に数カ月分の生活費を確保することが安心につながる
家計を守るためには、支出の透明化と優先順位付けが大切です。
社会保険料・住民税・住宅ローンの支払い対応 – 給料減少時の負担軽減方法や相談窓口の紹介
休職により給料が減少しても、社会保険料や住民税、住宅ローンの支払いは継続される場合が多いです。これらの負担を軽減するためには、各種支払いの猶予や減免制度を活用することが有効です。
下記のテーブルで具体的な対応策を整理します。
| 項目 | 対応策 | 相談先 |
|---|---|---|
| 社会保険料 | 減免申請・納付猶予 | 市区町村役所 |
| 住民税 | 分割納付・減免制度 | 市区町村役所 |
| 住宅ローン | 返済猶予・条件変更(リスケ) | 金融機関窓口 |
支払いが困難な場合は、早めに相談窓口へ連絡し、必要書類の準備や手続きを行いましょう。住宅ローンについては金融機関によって対応が異なるため、個別相談が欠かせません。社会保険料や住民税も、自治体の減免制度を積極的に確認しましょう。
休職保険や民間保険の活用事例 – 保険給付の受給条件や手続きのポイント
休職中は会社からの給料が減少する中で、民間の休職保険や医療保険、傷病手当金など公的制度を活用することで生活の安定を図ることができます。特にうつ病や適応障害などメンタル不調による休職の場合、保険の適用条件や申請手続きが重要です。
- 民間の休職保険や医療保険は、契約時の告知内容や加入条件を事前に確認
- 傷病手当金は、健康保険加入者が病気やケガで就業困難な場合に支給される制度で、標準報酬日額のおおむね6割が最長1年6カ月支給される
- 受給には医師の診断書や会社の休職証明が必要なため、早めに人事や保険会社へ相談・手続きを進める
公務員や教員の場合は、独自の休職制度や手当があるため、所属先の人事部門や共済組合に確認すると安心です。保険や給付金の活用で、休職期間中も生活費の不安を軽減できます。
休職開始から復職までの手続きと注意点
診断書取得と会社への提出 – 医師からの診断書のポイント、適切な提出時期と方法
休職を申請する際は、まず医師による診断書が必須です。診断書には「傷病名」「休職が必要な理由」「予想される休職期間」などが明記されていることが求められます。うつ病や適応障害などメンタル不調による休職の場合も、診断書の記載内容が非常に重要です。診断書の取得後は、速やかに会社の人事担当者や上司へ提出しましょう。書類の提出時期が遅れると、給与や傷病手当金の申請手続きに影響が出ることがあります。提出方法は原則として書面ですが、状況に応じて郵送やFAXの利用が認められる場合もあります。提出後は必ず受領の確認を行い、控えを保管しておくと安心です。
休職届・申請書類の準備と提出フロー – 必要書類の記載例や期限管理のコツ
診断書提出後は、会社指定の休職届や申請書類を用意します。多くの企業では「休職届」「休職願」「給与支給に関する申請書」など複数の書類が必要となります。記載内容の例としては、氏名・所属・休職理由・希望休職期間・医師の診断書添付などがあります。期限管理も重要なポイントで、提出期限を過ぎると手続きが遅れたり、給与支給に影響することがあります。下記のように手順を整理しておくとミスを防げます。
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 必要添付書類 |
|---|---|---|---|
| 休職届 | 人事部・上司 | 診断書提出後速やかに | 医師の診断書 |
| 給与関連申請 | 給与担当 | 会社規定に準じる | 診断書・休職届 |
| 傷病手当金申請 | 健康保険組合 | 休職開始後速やかに | 申請書・医師の意見書 |
また、休職期間の満了や復職時にも再度書類提出が必要となる場合があります。必ず会社の規則を確認し、不明点は人事部に問い合わせることが重要です。
復職時の面談・医師判断・会社対応 – 復職判定の流れと配慮事項、復帰後のフォロー体制
復職の際は、医師の復職可能判断がまず必要です。多くの企業では、復職前に人事担当者や産業医との面談が行われ、業務内容や勤務時間についての調整が検討されます。面談では、復職後の配慮事項や就業制限の有無、段階的な勤務復帰(短時間勤務や時差出勤など)について話し合われます。
復職判定の主な流れ
- 主治医による復職許可の診断書取得
- 会社への診断書提出
- 産業医・人事との面談実施
- 復職可否の最終判断および復帰計画の策定
復職後も、心身の健康維持や再発防止のために定期的なフォロー面談が設けられることが一般的です。うつ病や適応障害などメンタル不調からの復帰の場合、無理なく職場復帰できる環境作りが重要です。会社の支援制度や相談窓口も積極的に活用しましょう。
休職中のよくある疑問と詳細Q&A
休職給料に関する代表的質問 – 支給割合や期間、申請手続きの具体的な質問と回答
休職中の給料に関する悩みは多くの方が抱えています。特に「休職すると給料はどうなるのか」「給料は何割もらえるのか」「いつまで支給されるのか」といった疑問がよく寄せられます。下記のテーブルで代表的な質問と回答を整理しました。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 休職中の給料は支給される? | 多くの場合、会社規定により支給されませんが、就業規則や労働協約で支給されるケースもあります。 |
| 休職中の給与は何割? | 法律上の休業手当は平均賃金の60%ですが、会社によって異なります。 |
| 傷病手当金はいつからもらえる? | 連続した3日間の待機期間を経て、4日目から最長1年6か月支給されます。 |
| 申請に必要な書類は? | 医師の診断書、会社の証明書、健康保険証等が必要です。 |
ポイント
– 会社独自の規則が適用される場合もあるため、必ず就業規則を確認しましょう。
– 公務員や教員は、制度が異なるケースが多いため注意が必要です。
休職理由ごとの手続き・支給の違い – うつ病や適応障害など理由別の疑問と対応策
休職の理由によって、給料や手当の支給・手続きの流れは異なります。特に「うつ病」や「適応障害」などメンタル不調による休職の場合、会社にもよりますが、傷病手当金の申請が中心となります。
主な違いと対応策
– うつ病・適応障害の場合
– 医師の診断書が必須
– 傷病手当金の申請が可能(健康保険加入者)
– 労災認定される場合は労災保険給付も対象
– 業務外の病気やケガ
– 傷病手当金が主な補償
– 会社からの給与支給は原則停止
– 公務員・教員の場合
– 病気休暇や特別休職など独自の制度あり
– 支給割合や期間も民間とは異なる
注意点
– 傷病手当金と会社からの給与は同時に受け取れない場合があります。
– 申請期限や必要書類を事前に確認し、早めの手続きを心掛けましょう。
休職中のトラブル・困りごとと相談先 – 給料未払い・申請ミス・復職拒否など問題の解決策
休職中は「給料が支払われない」「傷病手当金の申請手続きでミスをした」「復職を拒否された」など、思いがけないトラブルが発生することも少なくありません。
発生しやすいトラブル例と対処法
- 給料未払い
- 会社の就業規則や労働契約書を確認し、内容に不明点があれば労働基準監督署に相談しましょう。
- 申請手続きミス
- 不備があった場合は、速やかに会社や健康保険組合に確認し、再提出を行います。
- 復職拒否や不当な扱い
- 産業医や人事担当者と面談し、必要に応じて労働局や弁護士へ相談するのも効果的です。
相談先リスト
– 労働基準監督署
– 健康保険組合
– 産業医・社内相談窓口
– 法律相談窓口・弁護士
ポイント
– 休職中の権利や制度を把握しておくことで、冷静に対応できます。
– 手続きや相談は早めに行い、不安な点は専門機関に確認しましょう。

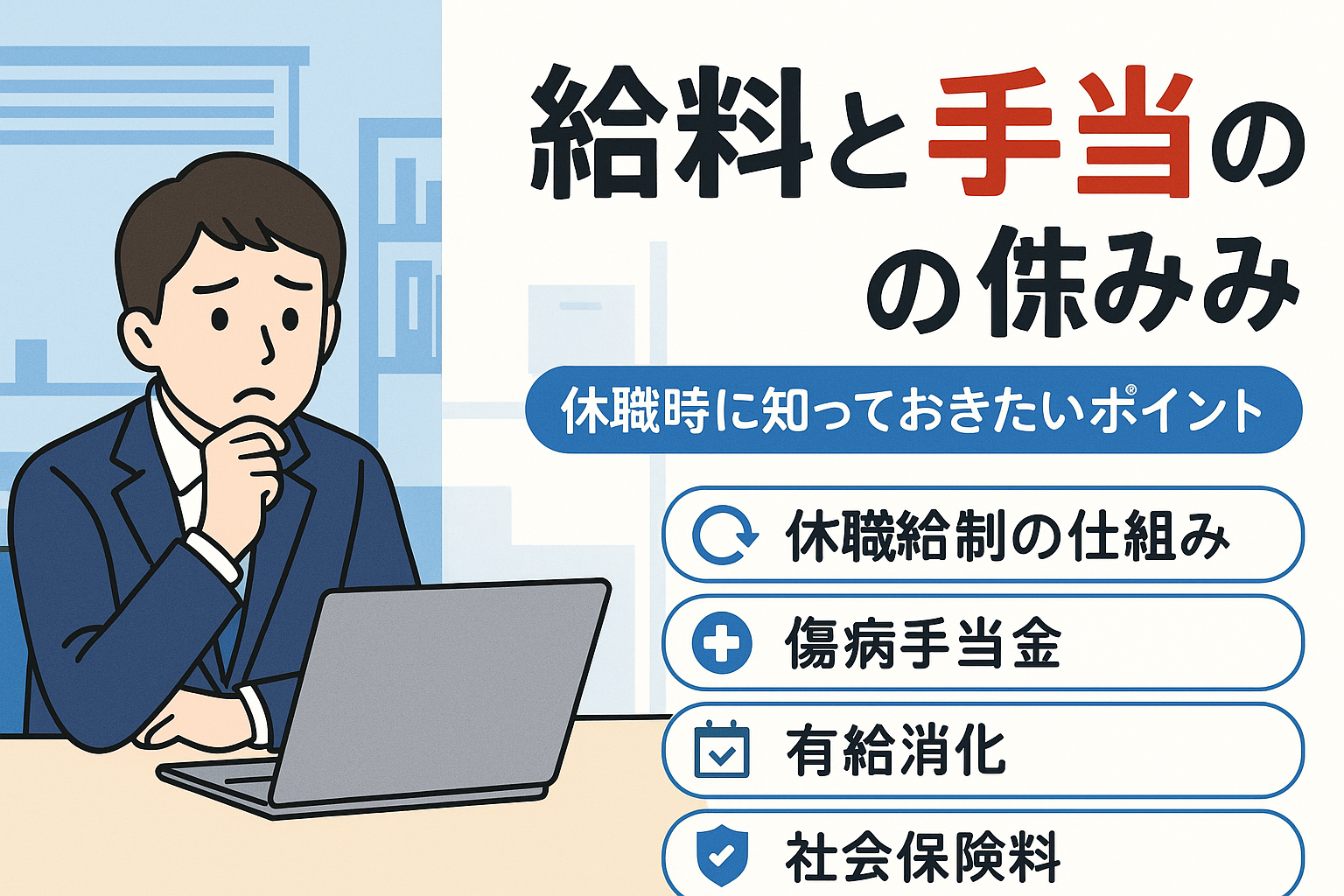


コメント